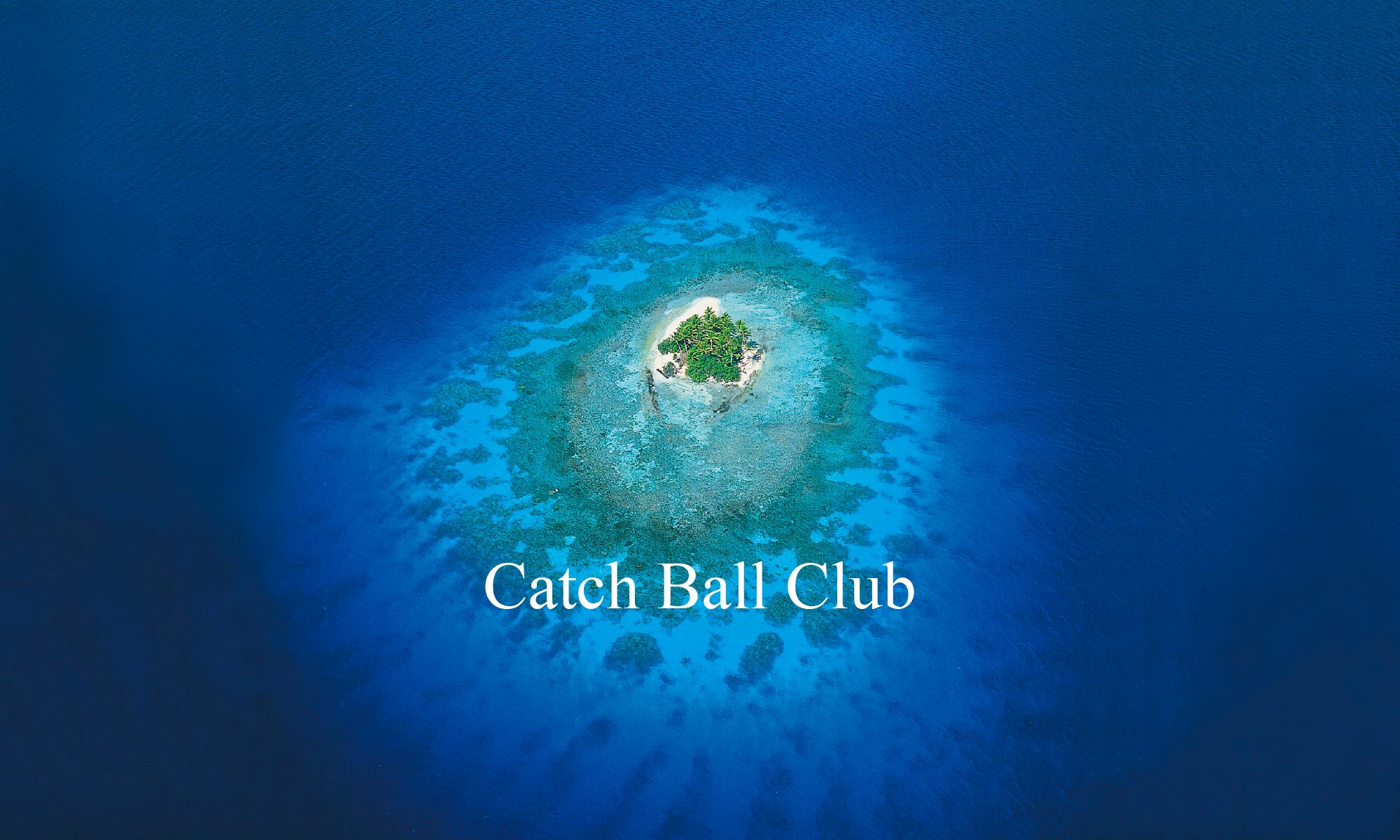「1+1>2」達成の必須条件
フィードバック機能を健全化する
☆
ラーニング・オーガニゼーション(学習する組織)を提唱するピーター・M・センゲは、その著書「最強組織の法則――新時代のチームワークとは何か」の冒頭で次のように語っています。
『人はたいてい何らかの時期に、すばらしい「チーム」の一員だった経験をもっている。仲間で力を合わせてすばらしい活動を生んだチーム――信頼し合い、互いの長所を生かし、弱点は補いあい、ひとりひとりの目標をこえた目標を共有し、目のさめるような成果をあげたチーム。(中略)あんな体験をもう一度味わってみたい、そんな思いで人生を歩んできた。(中略)
すばらしいチームははじめからすばらしかったわけではない。すばらしい成果を生むすべを、チームが学習したのである』とし、その“すべ”として、システム思考の基本要素に『フィードバック・プロセス』を挙げています。
最強組織を創り上げるプロは、チームワークを感動体験として語り、感動のチームワークこそ、人生をかけて求め続ける価値がある、と示唆してくれているように思われます。その観点に立てば、チームワークとは、組織目標達成のための手段や策といった狭義のテクニックの次元にとどまらず、皆の協働によって創り出される「芸術作品」として、つまり目指すべき目的そのものとして語るべきものだ考えます。そう考えれば、ようやく「一人ひとりが、人生というドラマの主人公」というセリフが腑に落ちてきます。
人間関係こそ「幸せの本舞台」だと思います。そこに、策や思惑が入り込めば、一気に不信が広がり、対話も出来ない場となってしまいます。人間関係を手段視してはなりません。
☆
私は、プロのPAミキサーとしてコンサートやディナーショーなどのイベントの音響を担当した経験があります。そこで私は、大事なことを学びました。あまり知られてはいませんが、音響の責務は、まず、第一に(何よりも)、登壇者やアーティスト達の耳元に、彼ら自身が発する声や音をきちんとフィードバックすることにあります。
なぜなら、大音量が交錯する環境においては、自分の声さえ聴き取れなくなり、普段のような自然な話ができなくなるからです。自分の出した楽器の音が心地良く聞こえなければ、心地良く演奏できなくなるからです。互いの声が聞こえなければ、ハーモニーを奏でることなど不可能だからです。
☆
実際に、大きな会場でマイクを使った方なら、一度は体験されたことがあるはずです。自分の声が遅れて聞こえてきたり、残響音が邪魔して、話しづらい、もしくは、歌いづらいことがあったはずです。
自分自身の声が聞こえにくいと、無意識に大声を出すことになります。すると、すぐに喉がかれることになります。水差しを多用する時は(熱弁のせいもありますが)、音響が最適でなく、出演者の耳に最適な音がフィードバックされていないのが原因です。観客のために大きな音を出そうとすればするほど、出演者には、普段の自然な感覚とは異なる異常環境になってしまうのです。
出演者が自分の想いを素直に表現できるかどうか、自分らしさを思い切り発揮できるかどうかは、まず、出演者自身に、自らの行為を確かめ、さらに、自らを高めていける「心地よい音=反応」が必要不可欠なのです。出演者のための音響が、結局、観客のための音響になるということです。それを忘れて、観客にパワフルな音を聴かせようとすればするほど、音源となる出演者たちの悲鳴に気づかなくなっていくのです。
チームを率いるすべての皆さまへ…。そのチームが、家族であれ、仲間であれ、同僚であれ、市民であれ、日々刻々、それぞれのドラマの主人公たちが、それぞれの個性を発揮しています。「チーム・プロファイリング」をおすすめするは、それぞれ独自のチームと主人公たちの強みを知ることであり、どんな反応が心地よいかを気づき合うことができるからです。さあ、そこからドラマ再開です。
Responsibility――
まさに、どんなレスポンスができるか。これこそがチームを率いる責任者の、また、次世代を育成する教育者の、本来の仕事のように思えてなりません。
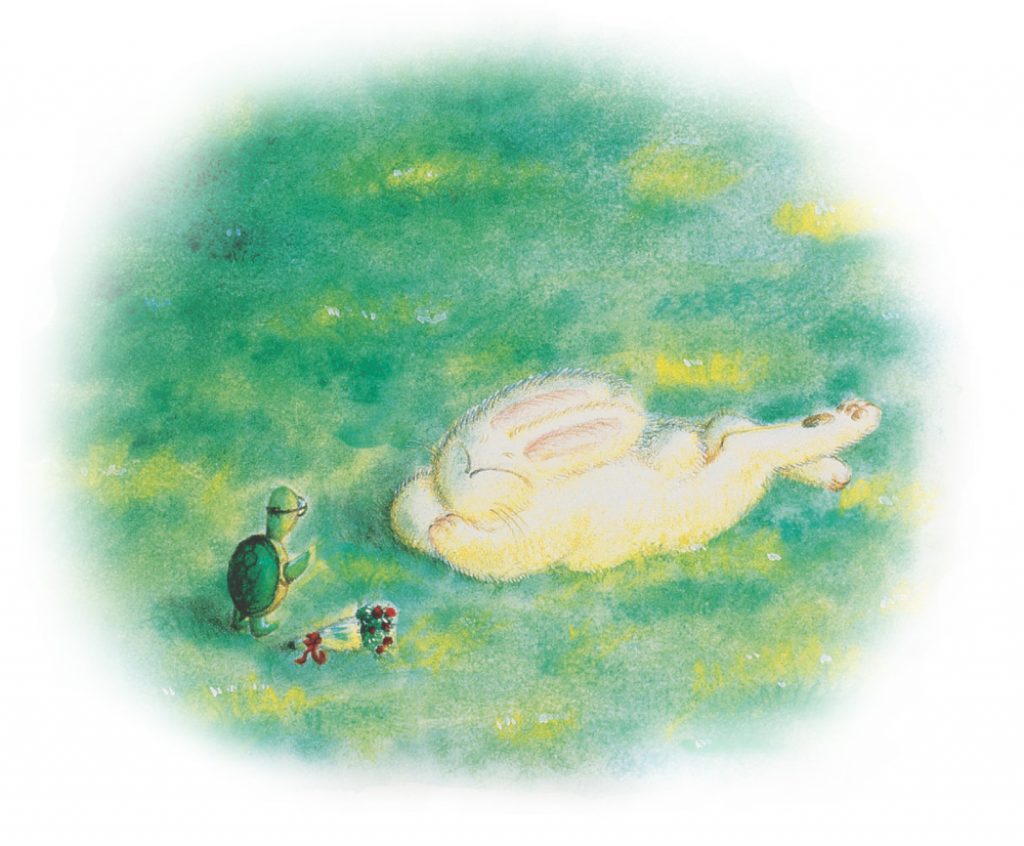
理事長:蔵満 正樹

チームワーク・プランナー/学術博士
特定非営利活動法人キャッチボールクラブ 理事長
個性別目標達成支援スーパーバイザー(ヒューマンサイエンス研究所)
最適組織編成支援パーソネル・アナリスト(組織人事監査協会)
《Haising》ライブ配信プランナー/舞台監督
◆経歴/
1957年大阪生まれ。コンサートやミュージカルなどの音響ミキサー、演出マネージャー兼舞台監督として活動。その後、雑誌記者、出版編集、広告プランナー、制作ディレクターを経て、1990年、Catch Ball Club活動開始。人と組織の対話支援システム開発会社を設立。特に、医療現場とサービス提供のためのコミュニケーション支援システムを開発し、人材教育と経営支援を行ってきた。1995年、FFS理論の開発者・小林惠智博士と出会い、米国ペンタゴンで採用された組織最適編成プログラムのアナリスト資格を取得。チーム・マネジメント(組織運営最適化支援)とストレス・マネジメント(人事運営最適化支援)、セルフコーチング(個性別目標達成支援)を実践。以降、医療におけるチームワークとストレスに関する研究を重ね、2006年、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 健康予防科学講座にて、新庄文明教授の指導のもと、博士(学術)の学位を取得。2009~2012年川崎医療福祉大学非常勤講師。2013年春、NPO法人キャッチボールクラブ設立。
現在、人と組織の成長を支援するコミュニケーション・システム開発、目標達成を楽しむ仕組みづくりとチームづくりを課題としたプログラム開発と業務支援を行っている。また、1+1>2をめざして「体験学習ライブ…ウサギとカメの対話物語」を主催し、ネットラジオ「エフエムひめ」番組制作、リアル会場・淀川区民センター研修講師、LINE公式アカウントでの通話による個別レクチャーを実施している。
ライフワークとして、リアル会場(オフライン)の舞台進行と、リモート(オンライン)のライブ配信プランナーとして、ハイブリッド配信のチームワークも推進している。
著書:「対話読本1:仲良しになるために」「対話読本2:主人公であるために」「対話読本3:生かし合うために」「歯の治療メニュー活用読本」「感動の不等式1+1>2」「ただ今マイクのテスト中!」「The Bible of FFS Method」
学位論文:「歯科スタッフの仕事に対する不満度に影響を与える個人要因に関する研究」論文要旨/論文概要
投稿論文:「医院経営における経営管理姿勢と経営状態、満足度との関連に関する調査」投稿論文
研究報告:「MMPG 歯科経営研究会:SYMPOSIUM 2008/これからの歯科医院経営の活路」統合冊子
開発アプリ:「Catch Ball System」「Monsing_for Bridal, for Dental」「Casting」「Menu321」「MenuMaker」
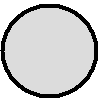
私は「ピーナッツ」です。
A=13, B=16, C=13, D=20, E=9, S=6
Copyright 1990-2026: Catch Ball Club, Masaki Kuramitsu. All rights reserved.